
年中行事
event

行事予定
schedule
| 令和7年度 | |
| 1月3日(金) | 年始会 ご祈祷札お届け |
|---|---|
| 2月24日(月・振替休日) | 地蔵尊祈願法要会 |
| 3月16日(日) | 午後 釈尊涅槃会法要―団子まき |
| 3月20日(木・春分の日) | 春彼岸法要会 |
| 5月25日(日) | 先住忌(50回忌)、常例法要、毘沙聞天(上杉謙信祈願仏)大祭 |
| 8月1日(金) | 新盆法要会 |
| 8月13日(水) | 盂蘭盆法要会、お盆迎え火、お墓参り |
| 9月23日(火・秋分の日) | 秋彼岸法要会 |
| 11月23日(日) | 覚鑁大師法要会、護持会総会 |
| 令和8年度 | |
| 1月1日(木) | 元朝ご祈祷法要会 |
| 1月2日(金) | 年始会 |
修正会(1月1日~3日)
正月 一日午前0時から三日までの3が日間、国家安穏、仏法興隆、皆様の一年間の平和な暮らしが過ごせるようにと祈願いたします。
一日、二日には寺年始として沢山の方がお参りに来られます。三日の日には祈念いたしました御祈祷札をご家庭にお配りしたします。
地蔵尊祈願法要会(2月24日(直前の日曜日))

古くからお寺に伝わっている延命子育地蔵尊祈願法要です。お子様の健やかな成長と健康で長生きが出来るようにとお地蔵様にお願いします。
その昔、亡くなった人を供養する為に「地蔵講」を結成して皆で亡くなられた家庭を見舞ってきました。また、普段は持ち回りで講員の家庭で集まって楽しみの場としたり、特に封建時代には民衆に許された旅の自由は神社参拝でしたので「講」を作り団体参拝をして村の人達との絆を結んできました。
地蔵様の滅罪生善の功徳を頂く為に今日まで続いております。
涅槃会(3月15日(直前の日曜日))

お釈迦様が亡くなられた日(2月15日)の法要会です。
新潟では月遅れの3月15日にその法要を行っている寺院が多いです。お釈迦様の涅槃像を掛け法恩の法要会です。
「団子撒き」と称して5色の団子とお菓子を供え、読経が終えると参拝に音連れ多人達に一斉に撒いて拾ってもらいお釈迦様の功徳を頂いてもらいます。団子はご飯の中に入れて食べる、または小さな袋を作って団子を2個から3個いれお守りとして身に着る。

彼岸法要会(3月21日(春分の日)9月23日(秋分の日))
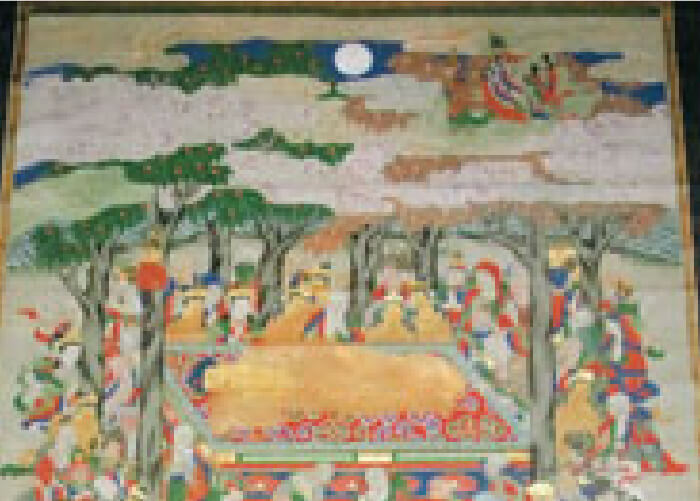
この世「此岸」(しがん)に対してあの世(悟りの境地である涅槃の世)を「彼岸」といい、太陽が真西に向かう日で阿弥陀仏の浄土でこの日に亡くなった人を弔う行事で、お参りされると功徳が授かると言われております。お墓参りには団子やおはぎを供えて先祖様に感謝を報告いたします。
毘沙門天大祭(5月最終日曜日)

大般若600巻転読と護摩壇を築いて護摩を焚き真言を誦し国家安穏、家内安全、商売繁盛、五穀豊穣、息災延命、福寿増長、身体健全、交通安全、厄難消除、必勝、心願成就を祈願いたします。
毘沙門天本尊は上杉謙信祈願仏で「難攻不落の居城は山岳にあり」との想いで山頂に佇んで民を見守っている姿です。
平成21年NHK大河ドラマのナレーションのところで兼続公が山頂に佇んでいる姿をイメージしてください。
新盆法要会・盂蘭盆法要会(8月1日・8月13日)

四方を竹の枝で精霊棚を設け死者の霊を供養いたします。
8月13日の夕方までに精霊をお迎えし、16日午前中までにお送りします。
新盆法要会は前年の7月31日から翌年の7月迄に亡くなられた方の初めての盆供養で死後の世界における苦痛を救う為と自分の苦痛を解く供養です。
お釈迦様の時代釈迦の10人弟子の一人目蓮尊者が我鬼道に落ちた母の痩せ衰えた姿を見て食べ物を与えようとしたが口元に持っていくと火炎となって食べることが出来ない。釈迦にすがって母の苦しみを救おうとしたが母の罪は重く容易ではない、10方の僧侶にお願いし百味の飲食で供養し、その力で救われたと言われております。
盆の文字は皿の上に分けると書きます。皿の上に胡瓜や茄子を細かく切って分けて盛って供養する---
ご先祖を供養する事、即ちお墓参りすることは親が居て自分が居る事、親への感謝に気付いたり、生きている喜びを家族の絆として感じることが出来る大切な日ではないでしょうか。
覚鑁大師法要会(11月12日)
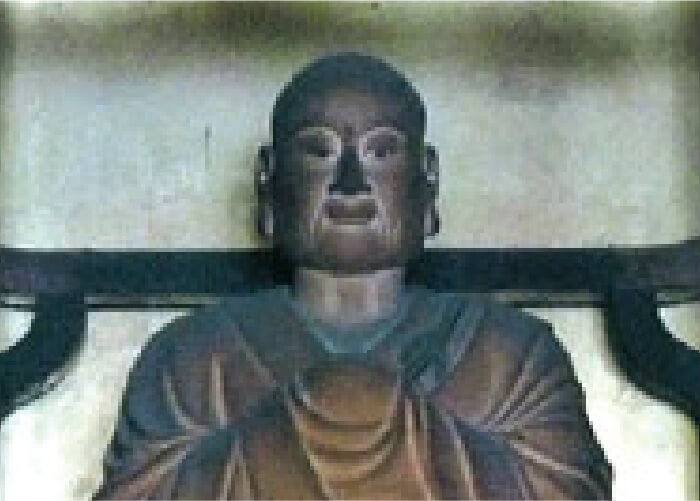
覚鑁大師は、真言宗の中興の祖として仰がれている高僧です。
真言宗が乱れこのままでは大変な事になると危惧し、紀州根来に円明寺(根来寺)を起こして真義真言宗を再興致しました。故に開山興教大師として崇められております。
報恩講とも呼ばれます。覚鑁大師の恩に報ずるための法要です。併せて1年間の無事に感謝し、ご先祖様に報告し来る年も良き年であるように祈願法要を厳修致してます。

